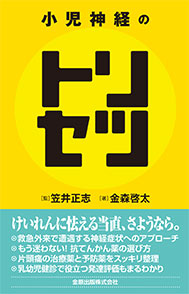Copyright© KANEHARA & Co., LTD. All Rights Reserved.
小児神経のトリセツ
けいれんに怯える当直はもう終わり! 神経の神髄はたったコレだけ

小児科外来でしばしば遭遇するけいれんやてんかん発作などの緊急性の高い病態と、頭痛や起立性調節障害といった慢性疾患の診療、さらには乳幼児健診での発達の評価まで、脳神経領域は小児科医の必修科目ともいえる。しかし「神経はニガテ!」と思われる方はかなり多い。そこで「トリセツ」は神経のむずかしい解剖・生理や専門的な検査を全部省きました!「神経はニガテ!」な方こそ読みたい、これなら分かる小児神経の手ほどき本。
Chapter1 救急外来で遭遇する症状別アプローチ
1. けいれん・意識障害
1. けいれんとは
2. けいれん・てんかん発作対応の事前準備
3. 呼吸と循環の評価と安定化
4. てんかん発作が持続しているかを見抜く
5. けいれん・てんかん発作を止める!
6. けいれんはいつまでに止めたい?
7. 原因検索
2. 頭痛
1. 一次性頭痛と二次性頭痛
2. 頭痛のRed Flag を見抜く!
3. 脳神経の診察
4. 頭痛パターンによる鑑別
3. 運動麻痺・筋力低下
1. 主訴
2. ギラン・バレー症候群の特徴と診断基準
3. 病歴聴取のポイント
4. 腱反射〈上腕二頭筋、上腕三頭筋、腕橈骨筋、膝蓋腱、アキレス腱〉
5. 筋力低下の評価方法
6. 運動麻痺・筋力低下をきたすその他の神経疾患
4. 失調
1. 失調とは
2. 急性小脳失調の特徴と診療のプロセス
5. 眼球運動障害・複視・眼瞼下垂
1. 主訴
2. 重症筋無力症の特徴と診療のプロセス
6. 頭部外傷
1. 頭部外傷での問診・診察
2. 頭部CT 検査を行うか
3. 虐待を見逃さないために
4. 親御さんへの配慮も忘れずに
Chapter2 非専門医が知っておくべき小児神経疾患
1. 熱性けいれん
1. 熱性けいれんについて知っておくべき知識
2. 熱性けいれんに対する検査
3. 熱性けいれんに対する処方
4. 保護者への説明の要点
2. 急性脳症
1. 急性脳症について知っておくべき知識
2. けいれん重積型(二相性)急性脳症
3. 熱性けいれんと急性脳症の鑑別
3. てんかん
1. てんかんについて知っておくべき知識
2. てんかん発作を見抜く
3. てんかんの分類
4. てんかん症候群の診断
5. 脳波検査の用いかた
6. てんかんの治療
7. 日常生活の注意点
4. 片頭痛
1. 片頭痛について知っておくべき知識
2. 片頭痛の診断
3. 片頭痛の治療
5. 緊張型頭痛
1. 緊張型頭痛について知っておくべき知識
2. 緊張型頭痛の診断
3. 緊張型頭痛の治療
6. 起立性調節障害
1. 起立性調節障害について知っておくべき知識
2. 起立性調節障害の診断
3. 起立性調節障害の治療
4. 心身症としての起立性調節障害
7. 神経発達症(発達障害)
1. 神経発達症を疑う症状
2. 診断に役立つ評価ツール
3. 神経発達症への関わり方
4. 神経発達症の分類
8. もやもや病
1. もやもや病の疑いかた
2. 検査
3. 治療
9. 脊髄性筋萎縮症
1. 脊髄性筋萎縮症の疑いかた
2. 検査
3. 治療
10. ギラン・バレー症候群
1. ギラン・バレー症候群の疑いかた
2. 検査
3. 治療
11. 重症筋無力症
1. 重症筋無力症の疑いかた
2. 検査
3. 治療
4. 注意点
12. 筋疾患〈筋ジストロフィー、先天性ミオパチー〉
1. 筋疾患の疑いかた
2. 確定診断のための検査
3. 筋疾患の各病型
13. 神経皮膚症候群〈神経線維腫症?型、結節性硬化症〉
1. 神経皮膚症候群の疑いかた
2. 神経線維腫症I型(NF1)
3. 結節性硬化症(TSC)
14. 重症心身障害児
1. 重症心身障害児の定義
2. 重症心身障害児の特徴
3. 重症心身障害児の評価
4. 筋緊張亢進に対する治療
Chapter3 乳幼児健診で役立つ発達の診かた
1. 発達に関する基本事項
1. 発達の種類
2. どんなときに神経疾患を考慮するか
3. 反射の時期
4. 言語遅滞の鑑別
5. 全身、特に皮膚の診察も忘れない
6. 要精査・要フォローの判断
7. 保護者への説明の仕方
2. 1 カ月児健診
1. 筋緊張
2. 原始反射
3. 3 〜 4 カ月児健診
1. 頸定(首の座り)
4. 6 〜 7 カ月児健診
1. 寝返り
2. お座り(座位)
3. ものに手を伸ばす(リーチング)
5. 9 〜 10 カ月児健診
1. はいはい
2. つかまり立ち
3. 喃語
6. 1 歳児健診
1. つたい歩き
2. 離乳食の完了
3. 模倣・指さし
7. 1 歳6 カ月児健診
1. 歩行
2. 発語
3. 応答の指さし
4. 共感的なやり取り
8. 2 歳児健診
1. 走る、階段を上がる
2. 2 語文
3. 指示の理解
4. 親と離れて遊ぶことができる
9. 3 歳児健診
1. 粗大運動
2. 3 語文
3. 自分の名前が言える
10. 5 歳児健診
1. 協調運動
2. コミュニケーション
3. ルールの理解
4. 情緒・行動
11. 健診で早期発見が重要な疾患
Chapter4 アドバンストレクチャー 世界一わかりやすい脳波の読み方
1. 小児科1 年生が脳波を読めるようになる必要があるか?
2. 睡眠ステージの判定
1. 覚醒と睡眠ステージの区別
3. 脳波異常
1. 突発異常波
2. 徐波
3. てんかん発作
巻末資料1 小児神経診療で使用する主な薬剤のまとめ
巻末資料2 小児神経チェックリスト
1. けいれん・意識障害
1. けいれんとは
2. けいれん・てんかん発作対応の事前準備
3. 呼吸と循環の評価と安定化
4. てんかん発作が持続しているかを見抜く
5. けいれん・てんかん発作を止める!
6. けいれんはいつまでに止めたい?
7. 原因検索
2. 頭痛
1. 一次性頭痛と二次性頭痛
2. 頭痛のRed Flag を見抜く!
3. 脳神経の診察
4. 頭痛パターンによる鑑別
3. 運動麻痺・筋力低下
1. 主訴
2. ギラン・バレー症候群の特徴と診断基準
3. 病歴聴取のポイント
4. 腱反射〈上腕二頭筋、上腕三頭筋、腕橈骨筋、膝蓋腱、アキレス腱〉
5. 筋力低下の評価方法
6. 運動麻痺・筋力低下をきたすその他の神経疾患
4. 失調
1. 失調とは
2. 急性小脳失調の特徴と診療のプロセス
5. 眼球運動障害・複視・眼瞼下垂
1. 主訴
2. 重症筋無力症の特徴と診療のプロセス
6. 頭部外傷
1. 頭部外傷での問診・診察
2. 頭部CT 検査を行うか
3. 虐待を見逃さないために
4. 親御さんへの配慮も忘れずに
Chapter2 非専門医が知っておくべき小児神経疾患
1. 熱性けいれん
1. 熱性けいれんについて知っておくべき知識
2. 熱性けいれんに対する検査
3. 熱性けいれんに対する処方
4. 保護者への説明の要点
2. 急性脳症
1. 急性脳症について知っておくべき知識
2. けいれん重積型(二相性)急性脳症
3. 熱性けいれんと急性脳症の鑑別
3. てんかん
1. てんかんについて知っておくべき知識
2. てんかん発作を見抜く
3. てんかんの分類
4. てんかん症候群の診断
5. 脳波検査の用いかた
6. てんかんの治療
7. 日常生活の注意点
4. 片頭痛
1. 片頭痛について知っておくべき知識
2. 片頭痛の診断
3. 片頭痛の治療
5. 緊張型頭痛
1. 緊張型頭痛について知っておくべき知識
2. 緊張型頭痛の診断
3. 緊張型頭痛の治療
6. 起立性調節障害
1. 起立性調節障害について知っておくべき知識
2. 起立性調節障害の診断
3. 起立性調節障害の治療
4. 心身症としての起立性調節障害
7. 神経発達症(発達障害)
1. 神経発達症を疑う症状
2. 診断に役立つ評価ツール
3. 神経発達症への関わり方
4. 神経発達症の分類
8. もやもや病
1. もやもや病の疑いかた
2. 検査
3. 治療
9. 脊髄性筋萎縮症
1. 脊髄性筋萎縮症の疑いかた
2. 検査
3. 治療
10. ギラン・バレー症候群
1. ギラン・バレー症候群の疑いかた
2. 検査
3. 治療
11. 重症筋無力症
1. 重症筋無力症の疑いかた
2. 検査
3. 治療
4. 注意点
12. 筋疾患〈筋ジストロフィー、先天性ミオパチー〉
1. 筋疾患の疑いかた
2. 確定診断のための検査
3. 筋疾患の各病型
13. 神経皮膚症候群〈神経線維腫症?型、結節性硬化症〉
1. 神経皮膚症候群の疑いかた
2. 神経線維腫症I型(NF1)
3. 結節性硬化症(TSC)
14. 重症心身障害児
1. 重症心身障害児の定義
2. 重症心身障害児の特徴
3. 重症心身障害児の評価
4. 筋緊張亢進に対する治療
Chapter3 乳幼児健診で役立つ発達の診かた
1. 発達に関する基本事項
1. 発達の種類
2. どんなときに神経疾患を考慮するか
3. 反射の時期
4. 言語遅滞の鑑別
5. 全身、特に皮膚の診察も忘れない
6. 要精査・要フォローの判断
7. 保護者への説明の仕方
2. 1 カ月児健診
1. 筋緊張
2. 原始反射
3. 3 〜 4 カ月児健診
1. 頸定(首の座り)
4. 6 〜 7 カ月児健診
1. 寝返り
2. お座り(座位)
3. ものに手を伸ばす(リーチング)
5. 9 〜 10 カ月児健診
1. はいはい
2. つかまり立ち
3. 喃語
6. 1 歳児健診
1. つたい歩き
2. 離乳食の完了
3. 模倣・指さし
7. 1 歳6 カ月児健診
1. 歩行
2. 発語
3. 応答の指さし
4. 共感的なやり取り
8. 2 歳児健診
1. 走る、階段を上がる
2. 2 語文
3. 指示の理解
4. 親と離れて遊ぶことができる
9. 3 歳児健診
1. 粗大運動
2. 3 語文
3. 自分の名前が言える
10. 5 歳児健診
1. 協調運動
2. コミュニケーション
3. ルールの理解
4. 情緒・行動
11. 健診で早期発見が重要な疾患
Chapter4 アドバンストレクチャー 世界一わかりやすい脳波の読み方
1. 小児科1 年生が脳波を読めるようになる必要があるか?
2. 睡眠ステージの判定
1. 覚醒と睡眠ステージの区別
3. 脳波異常
1. 突発異常波
2. 徐波
3. てんかん発作
巻末資料1 小児神経診療で使用する主な薬剤のまとめ
巻末資料2 小児神経チェックリスト
小児神経は、小児科のサブスペシャリティの中でも幅が広く、common diseasesもたくさんあります。そのため、まだ専門領域を持たない専攻医や、神経を非専門とする一般小児科医にとって関わる機会の多い領域です。熱性けいれんなどの救急外来でしばしば遭遇する緊急性の高い疾患のほか、頭痛や起立性調節障害といった小児科外来でよく目にする慢性疾患もあります。さらには、乳幼児健診における発達の評価も、サブスペシャリティ領域としては、小児神経に分類されることでしょう。
このように、多くの小児科医が避けて通れない小児神経領域ですが、解剖・生理が複雑に感じるせいでしょうか、「神経はニガテ」という声を聞く機会は少なくありません。
本書は「小児科トリセツ」シリーズの基本コンセプトにしたがって、小児科1年生にも気軽に読むことができて、なおかつ実践に役立つ情報を、簡潔にまとめました。
Chapter1ではけいれんや意識障害といった救急外来で主に遭遇する症状について、Chapter2では神経を専門としていなくても小児科医ならば知っておくべき小児神経疾患について、Chapter3では乳幼児健診で役立つ発達について解説しています。
とにかく実践に役立つことを第一に考えて執筆しました。一般的な小児神経の参考書の主役になるような、「ザ・神経疾患」の希少疾患・難病については、必要最低限の記載に留めています。それとは反対に、熱性けいれんや起立性調節障害、片頭痛といったcommon diseasesともいうべき疾患は、一般的な小児神経の参考書では扱いが小さいですが、非専門の小児科医を対象とするならば特に重要であると考え、本書では力を入れて解説しています。
また、読者のなかには、「頭部画像検査や脳波検査の詳細な判定方法について学びたい」と考えている医師もいるかもしれません。そのような内容を期待して本書を手にとっていただいた方には申し訳ないのですが、これらのスキルは小児科1年生を含めたすべての小児科医が知っておかなければいけないものとは考えておりませんので、本編には含めておりません。
しかし、脳波は非常にリクエストの多いテーマでもありましたので、本編とは別にアドバンストレクチャーとして「世界一わかりやすい脳波の読みかた」と銘打ってエッセンスを解説しています。興味があればご一読ください。
本書は小難しい話は抜きにして、手軽に参照できることと、しっかり臨床の武器になることを意識して執筆しました。「神経はニガテ」と感じながらも周りに相談できる先生も少なく困っている読者のみなさまが、「この本があればなんとか小児神経疾患に立ち向かっていける」と言ってもらえるような一冊にすることを目指しました。
少しでも本書がみなさまの臨床の支えになりますことを願っています。
2025年9月
岩手県立療育センター 小児科医長
著者 金森 啓太
このように、多くの小児科医が避けて通れない小児神経領域ですが、解剖・生理が複雑に感じるせいでしょうか、「神経はニガテ」という声を聞く機会は少なくありません。
本書は「小児科トリセツ」シリーズの基本コンセプトにしたがって、小児科1年生にも気軽に読むことができて、なおかつ実践に役立つ情報を、簡潔にまとめました。
Chapter1ではけいれんや意識障害といった救急外来で主に遭遇する症状について、Chapter2では神経を専門としていなくても小児科医ならば知っておくべき小児神経疾患について、Chapter3では乳幼児健診で役立つ発達について解説しています。
とにかく実践に役立つことを第一に考えて執筆しました。一般的な小児神経の参考書の主役になるような、「ザ・神経疾患」の希少疾患・難病については、必要最低限の記載に留めています。それとは反対に、熱性けいれんや起立性調節障害、片頭痛といったcommon diseasesともいうべき疾患は、一般的な小児神経の参考書では扱いが小さいですが、非専門の小児科医を対象とするならば特に重要であると考え、本書では力を入れて解説しています。
また、読者のなかには、「頭部画像検査や脳波検査の詳細な判定方法について学びたい」と考えている医師もいるかもしれません。そのような内容を期待して本書を手にとっていただいた方には申し訳ないのですが、これらのスキルは小児科1年生を含めたすべての小児科医が知っておかなければいけないものとは考えておりませんので、本編には含めておりません。
しかし、脳波は非常にリクエストの多いテーマでもありましたので、本編とは別にアドバンストレクチャーとして「世界一わかりやすい脳波の読みかた」と銘打ってエッセンスを解説しています。興味があればご一読ください。
本書は小難しい話は抜きにして、手軽に参照できることと、しっかり臨床の武器になることを意識して執筆しました。「神経はニガテ」と感じながらも周りに相談できる先生も少なく困っている読者のみなさまが、「この本があればなんとか小児神経疾患に立ち向かっていける」と言ってもらえるような一冊にすることを目指しました。
少しでも本書がみなさまの臨床の支えになりますことを願っています。
2025年9月
岩手県立療育センター 小児科医長
著者 金森 啓太
- 医書.jpで購入される方は
こちらから (外部サイトに移動します) - m3.comで購入される方は
こちらから (外部サイトに移動します)
脳波が宇宙人の暗号に見える方へ(私もです)
小児神経は「なんだか難しそう」と感じていた小児科医のみなさんへ。ご安心ください。『小児神経のトリセツ』がついに完成しました。本書は実践的な切り口から小児神経を学べ、かつ読み切れるボリュームで全体像を把握できる一冊です。
今回のハイライトは、なんといってもてんかんです。これは本当に奥が深い領域で、専門医でも日々新しい知見をアップデートしている領域です。特に発作の「起始」、つまり最初の情報が何よりも重要だということを、てんかんの章ではしつこく(いや、丁寧に!)解説しています。「起始」をしっかり評価することで、診断の半分は終わったようなものです。
もうひとつのハイライトは、「世界一わかりやすい脳波」の読み方です。これは少し大げさな表現かもしれませんが、てんかんを疑う症例で、脳波をどのように読み解くか、その考え方をこれ以上分かりやすく説明した本はないと思います。脳波の波形が宇宙人の暗号に見えていた人も、きっとこれで「なるほど!」と思えるはずです。もし購入を迷っているなら、まずこのChapterだけでも読んでみてください。きっと靄が晴れるはずです。
最後に小児科医として絶対に忘れてはならない重要な知恵を、ひとつお伝えします。それは、「迷ったら治療しない」ということ。これは決して投げやりな姿勢ではありません。治療は“する”より“しない”判断のほうが難しいのです。安易な治療が子どもに不要な負担をかけることを避けるための、慎重かつ勇気ある判断です。小児神経と感染症に相通ずる部分です。
小児神経、あまり神経質にならずにトリセツ読む。
兵庫県立こども病院小児救命救急センター長&感染対策部長
監修 笠井 正志
小児神経は「なんだか難しそう」と感じていた小児科医のみなさんへ。ご安心ください。『小児神経のトリセツ』がついに完成しました。本書は実践的な切り口から小児神経を学べ、かつ読み切れるボリュームで全体像を把握できる一冊です。
今回のハイライトは、なんといってもてんかんです。これは本当に奥が深い領域で、専門医でも日々新しい知見をアップデートしている領域です。特に発作の「起始」、つまり最初の情報が何よりも重要だということを、てんかんの章ではしつこく(いや、丁寧に!)解説しています。「起始」をしっかり評価することで、診断の半分は終わったようなものです。
もうひとつのハイライトは、「世界一わかりやすい脳波」の読み方です。これは少し大げさな表現かもしれませんが、てんかんを疑う症例で、脳波をどのように読み解くか、その考え方をこれ以上分かりやすく説明した本はないと思います。脳波の波形が宇宙人の暗号に見えていた人も、きっとこれで「なるほど!」と思えるはずです。もし購入を迷っているなら、まずこのChapterだけでも読んでみてください。きっと靄が晴れるはずです。
最後に小児科医として絶対に忘れてはならない重要な知恵を、ひとつお伝えします。それは、「迷ったら治療しない」ということ。これは決して投げやりな姿勢ではありません。治療は“する”より“しない”判断のほうが難しいのです。安易な治療が子どもに不要な負担をかけることを避けるための、慎重かつ勇気ある判断です。小児神経と感染症に相通ずる部分です。
小児神経、あまり神経質にならずにトリセツ読む。
兵庫県立こども病院小児救命救急センター長&感染対策部長
監修 笠井 正志