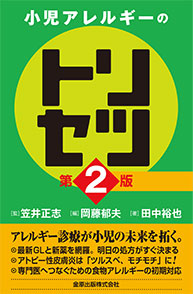Copyright© KANEHARA & Co., LTD. All Rights Reserved.
小児アレルギーのトリセツ 第2版
臨床現場の即戦力!小児アレルギー診療の「王道」がついに改訂

小児アレルギー診療のド定番がアップグレード! 最新のガイドラインの内容や新薬のデータもこの一冊に凝縮。アナフィラキシーの緊急対応からコモンな湿疹や喘息診療、専門医へつなげるための食物アレルギー診療まで、小児アレルギーの知識をスッキリと整理。現場で迷わないためのフローチャートで、アレルギー診療の初動から長期フォローまでの道筋がみえる。将来にわたってアレルギーから子どもを守るためのトリセツ。
Chapter 1 小児アレルギー診療の原則
1.子どものアレルギーを診るための基本事項
1 なぜアレルギーを診るのか=common disease だから
2 子どものアレルギーを診るときの大原則
3 アレルギーの概念・病態・発症の機序〈免疫とメカニズム〉
4 アレルギーの診断
2.子どものアレルギーに使う薬剤の基礎知識
1 上手に薬を使いこなすための7 ルール
2 薬剤各論
3 処方の実際
Chapter 2 小児アレルギー診療の実践
1.アナフィラキシーへの対応をマスターする
1 アレルギー症状の対応
2 初期対応後にするべきこと
2.気管支喘息をマスターする
1 医療機関における急性増悪(喘息発作)の対応
2 長期管理:二度と急性増悪(入院)を起こさせない!
3.湿疹の診かた〜子どもの肌をツルツルにする〜
1 湿疹をきれいにすること
2 湿疹をきれいにするやり方:スキンケア+抗炎症剤外用が基本!
3 アトピー性皮膚炎で注意すべき合併症
4.専門医へつなぐ食物アレルギー診療
1 アウトライン
2 食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎
3 即時型の食物アレルギーの診療
4 経口免疫療法
●食品別・食物アレルギーのトリセツ
5.その他のIgE 依存性食物アレルギー〜花粉-食物アレルギー症候群・食物依存性運動誘発アナフィラキシー〜
1 花粉-食物アレルギー症候群
2 食物依存性運動誘発アナフィラキシー
6.食物蛋白誘発胃腸症(消化管アレルギー)の診かた
1 消化管アレルギーとは
2 消化管アレルギーの分類と病態
3 消化管アレルギーの診断・治療
4 診断後の対応
7.鼻炎、結膜炎の診かた〜鼻水や鼻づまりを見たら、鼻を診る、眼がかゆいなら眼も診る〜
1 アレルギー性鼻炎をなぜ診る必要があるのか
2 診断する
3 重症度を決定する
4 アレルギー性鼻炎への対応
5 アレルギー性結膜炎への対応
6 花粉症の診かた
8.子どもの未来を変える舌下免疫療
1 アレルギーの子どもにアレルゲン免疫療法を行うことは正義である
2 舌下免疫療法の効果と安全性
3 舌下免疫療法の実際
9.薬剤による過敏反応
1 薬疹と薬剤アレルギー
2 重症薬疹の特徴〜皮膚科医以外が判断するために
3 即時型、軽症の薬疹(遅延型)への対応
4 臨床でよく経験する薬剤〜抗菌薬、造影剤、解熱鎮痛薬、局所麻酔薬
10.アレルギーをもつ子どもへの予防接種
1 基本的な考え方
2 食物アレルギー患者への予防接種
11.蕁麻疹の診かた
1 蕁麻疹の診断
2 蕁麻疹の治療
巻末資料 筆者厳選の頻用アレルギー治療薬のトリセツ
1.子どものアレルギーを診るための基本事項
1 なぜアレルギーを診るのか=common disease だから
2 子どものアレルギーを診るときの大原則
3 アレルギーの概念・病態・発症の機序〈免疫とメカニズム〉
4 アレルギーの診断
2.子どものアレルギーに使う薬剤の基礎知識
1 上手に薬を使いこなすための7 ルール
2 薬剤各論
3 処方の実際
Chapter 2 小児アレルギー診療の実践
1.アナフィラキシーへの対応をマスターする
1 アレルギー症状の対応
2 初期対応後にするべきこと
2.気管支喘息をマスターする
1 医療機関における急性増悪(喘息発作)の対応
2 長期管理:二度と急性増悪(入院)を起こさせない!
3.湿疹の診かた〜子どもの肌をツルツルにする〜
1 湿疹をきれいにすること
2 湿疹をきれいにするやり方:スキンケア+抗炎症剤外用が基本!
3 アトピー性皮膚炎で注意すべき合併症
4.専門医へつなぐ食物アレルギー診療
1 アウトライン
2 食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎
3 即時型の食物アレルギーの診療
4 経口免疫療法
●食品別・食物アレルギーのトリセツ
5.その他のIgE 依存性食物アレルギー〜花粉-食物アレルギー症候群・食物依存性運動誘発アナフィラキシー〜
1 花粉-食物アレルギー症候群
2 食物依存性運動誘発アナフィラキシー
6.食物蛋白誘発胃腸症(消化管アレルギー)の診かた
1 消化管アレルギーとは
2 消化管アレルギーの分類と病態
3 消化管アレルギーの診断・治療
4 診断後の対応
7.鼻炎、結膜炎の診かた〜鼻水や鼻づまりを見たら、鼻を診る、眼がかゆいなら眼も診る〜
1 アレルギー性鼻炎をなぜ診る必要があるのか
2 診断する
3 重症度を決定する
4 アレルギー性鼻炎への対応
5 アレルギー性結膜炎への対応
6 花粉症の診かた
8.子どもの未来を変える舌下免疫療
1 アレルギーの子どもにアレルゲン免疫療法を行うことは正義である
2 舌下免疫療法の効果と安全性
3 舌下免疫療法の実際
9.薬剤による過敏反応
1 薬疹と薬剤アレルギー
2 重症薬疹の特徴〜皮膚科医以外が判断するために
3 即時型、軽症の薬疹(遅延型)への対応
4 臨床でよく経験する薬剤〜抗菌薬、造影剤、解熱鎮痛薬、局所麻酔薬
10.アレルギーをもつ子どもへの予防接種
1 基本的な考え方
2 食物アレルギー患者への予防接種
11.蕁麻疹の診かた
1 蕁麻疹の診断
2 蕁麻疹の治療
巻末資料 筆者厳選の頻用アレルギー治療薬のトリセツ
<はじめに>
『小児アレルギーのトリセツ』初版を世に出てから、瞬く間に月日が流れました。望外にも、全国の小児医療に携わる多くの先生方に本書を手にとっていただき、日々の診療でご活用いただいているとのお声を多数頂戴しました。この場をお借りして、読者のみなさまに心より御礼申し上げます。みなさまからの温かい反響が、今回の改訂第2版を上梓する大きな原動力となりました。
初版の執筆当時、私は兵庫県立こども病院のアレルギー科として、専門医療の最前線に身を置いていました。そして今、私は地域医療の現場であるクリニックの医師として、日々子どもたちとそのご家族に向き合っています。
専門医療機関から、地域のクリニックへと主戦場を移したことで、私の視点も大きく変化しました。アレルギー診療は、決して専門医だけのものではありません。「咳がとまらない」「鼻水がずっと出ている」「肌がカサカサしている」といった、ありふれた主訴で訪れる子どもたちのなかに、気管支喘息やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎が隠れていることは日常茶飯事です。一般小児診療とアレルギー診療は切り離すことのできない、まさに表裏一体の関係にあることを、開業医となった今、あらためて痛感しています。小児科医にとって、アレルギー診療は特別なスキルではなく、必須のコモンスキルなのです。
この数年間で、アレルギー診療を取り巻く環境は目まぐるしく進化しました。次々と新しい治療薬が登場し、私たちの選択肢は格段に広がりました。一方で、その選択肢をいかに適切に使いこなすか、専門家としての知識のアップデートが常に求められます。本書では、最新の薬剤について、実臨床に即した形で解説を加えました。
また、各種ガイドラインも大きく改訂されました。第2版では、これらの変更点を的確に反映し、読者の方が迷うことなく標準治療を実践できるよう内容を刷新しました。
さらに、近年注目を集めている食物蛋白誘発胃腸症(消化管アレルギー)や、アレルギー疾患発症予防のアプローチについても、最新の知見を盛り込んでいます。診る機会が非常に多い花粉症についてはすぐに使える形で示しています。これらの新しい領域は、患者さんやご家族の関心も高く、小児に携わるすべての医療者が的確な情報を提供していく責務があると考えています。
今回の改訂にあたり、私が最もこだわったのは、初版でご好評いただいた「トリセツ」としての魂を失わないことでした。私が本書に込めた想いは、初版の序文に書いたとおり、「プロとしての適切な対応」を「迅速に」誰でも提供できるマニュアルであることです。多忙を極める外来診療の現場で、ポケットや白衣の片隅からサッと取り出し、知りたい情報を瞬時に確認できる手軽さ。このコンセプトは、今回の改訂でも一切揺らいでいません。
本書は、いわば「正常進化」を遂げました。核となるコンセプトやマニュアル本としての使いやすさはそのままに、最新の医学的エビデンスと、開業医として得た新たな臨床の知恵を随所に織り込んでいます。情報の質と量をアップデートしながらも、読者の方の負担にならないよう、情報の整理と表現には最後まで心を砕きました。
本書が、アレルギー診療の道を志す若手の先生方にとって心強い道標となり、また、すでに第一線でご活躍の先生方にとっては知識を再確認し、明日からの診療に新たな視点をもたらす一助となれば、著者としてこれに勝る喜びはありません。
最後になりますが、本書の監修を快くお引き受けくださり、常に温かいご指導を賜りました笠井正志先生、岡藤郁夫先生、そして出版にご尽力いただいた中立稔生様をはじめとして金原出版のみなさまに、あらためて深く感謝申し上げます。
この「小児アレルギーのトリセツ」が、アレルギーに悩む多くの子どもたちとそのご家族の笑顔につながることを、心から願っています。
2025年盛夏
たなか小児科アレルギー科 院長
著者 田中 裕也
『小児アレルギーのトリセツ』初版を世に出てから、瞬く間に月日が流れました。望外にも、全国の小児医療に携わる多くの先生方に本書を手にとっていただき、日々の診療でご活用いただいているとのお声を多数頂戴しました。この場をお借りして、読者のみなさまに心より御礼申し上げます。みなさまからの温かい反響が、今回の改訂第2版を上梓する大きな原動力となりました。
初版の執筆当時、私は兵庫県立こども病院のアレルギー科として、専門医療の最前線に身を置いていました。そして今、私は地域医療の現場であるクリニックの医師として、日々子どもたちとそのご家族に向き合っています。
専門医療機関から、地域のクリニックへと主戦場を移したことで、私の視点も大きく変化しました。アレルギー診療は、決して専門医だけのものではありません。「咳がとまらない」「鼻水がずっと出ている」「肌がカサカサしている」といった、ありふれた主訴で訪れる子どもたちのなかに、気管支喘息やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎が隠れていることは日常茶飯事です。一般小児診療とアレルギー診療は切り離すことのできない、まさに表裏一体の関係にあることを、開業医となった今、あらためて痛感しています。小児科医にとって、アレルギー診療は特別なスキルではなく、必須のコモンスキルなのです。
この数年間で、アレルギー診療を取り巻く環境は目まぐるしく進化しました。次々と新しい治療薬が登場し、私たちの選択肢は格段に広がりました。一方で、その選択肢をいかに適切に使いこなすか、専門家としての知識のアップデートが常に求められます。本書では、最新の薬剤について、実臨床に即した形で解説を加えました。
また、各種ガイドラインも大きく改訂されました。第2版では、これらの変更点を的確に反映し、読者の方が迷うことなく標準治療を実践できるよう内容を刷新しました。
さらに、近年注目を集めている食物蛋白誘発胃腸症(消化管アレルギー)や、アレルギー疾患発症予防のアプローチについても、最新の知見を盛り込んでいます。診る機会が非常に多い花粉症についてはすぐに使える形で示しています。これらの新しい領域は、患者さんやご家族の関心も高く、小児に携わるすべての医療者が的確な情報を提供していく責務があると考えています。
今回の改訂にあたり、私が最もこだわったのは、初版でご好評いただいた「トリセツ」としての魂を失わないことでした。私が本書に込めた想いは、初版の序文に書いたとおり、「プロとしての適切な対応」を「迅速に」誰でも提供できるマニュアルであることです。多忙を極める外来診療の現場で、ポケットや白衣の片隅からサッと取り出し、知りたい情報を瞬時に確認できる手軽さ。このコンセプトは、今回の改訂でも一切揺らいでいません。
本書は、いわば「正常進化」を遂げました。核となるコンセプトやマニュアル本としての使いやすさはそのままに、最新の医学的エビデンスと、開業医として得た新たな臨床の知恵を随所に織り込んでいます。情報の質と量をアップデートしながらも、読者の方の負担にならないよう、情報の整理と表現には最後まで心を砕きました。
本書が、アレルギー診療の道を志す若手の先生方にとって心強い道標となり、また、すでに第一線でご活躍の先生方にとっては知識を再確認し、明日からの診療に新たな視点をもたらす一助となれば、著者としてこれに勝る喜びはありません。
最後になりますが、本書の監修を快くお引き受けくださり、常に温かいご指導を賜りました笠井正志先生、岡藤郁夫先生、そして出版にご尽力いただいた中立稔生様をはじめとして金原出版のみなさまに、あらためて深く感謝申し上げます。
この「小児アレルギーのトリセツ」が、アレルギーに悩む多くの子どもたちとそのご家族の笑顔につながることを、心から願っています。
2025年盛夏
たなか小児科アレルギー科 院長
著者 田中 裕也
- 医書.jpで購入される方は
こちらから (外部サイトに移動します) - m3.comで購入される方は
こちらから (外部サイトに移動します)
<監修のことば>
偉大な教師は心に火をつける
アレルギー治療において、患者教育は薬物療法と同じくらい重要です。日々のケアを患者さんご自身が理解し、実践できるようなわかりやすい情報提供は欠かせません。そのためには、私たち医療者自身が正確な知識を身につけ、常に学び続けることが不可欠です。
「アレルギーは誰でもできる。それをより質高く実践すること」。この命題を多くの医療者に伝えるため、著者である田中裕也先生は常に情熱的に教育活動に取り組んでいます。
一番印象に残っているのは、KOBEセミナー*でのスキンケア指導ワークショップです。スキンケアの要点はp.82の図5にも記載されています。「石けんの泡で洗う」というシンプルな言葉だけでは、経験の少ない専攻医が具体的なイメージをもって患者指導を行うのは難しいものです。田中先生は、実際にバケツを使って「泡立てる」ことを楽しく実演してくださいました。その生き生きとした指導に、専攻医たちも夢中になっていました。まさに、偉大な教師の姿がそこにはありました。
教育の本質は、教える側の「どうしても伝えたい」という情熱が、学ぶ側の心に火をつけることにあると私は考えます。本書もまた、単なる情報の羅列ではありません。読者が自ら学び、成長しようとする力を育む、実践的な指南書となることを目指したものです。ぜひ、本書を通してアレルギー診療の新たな扉を開いてください。
*KOBEセミナーとは約10年前から続いている神戸中央市民病院小児科と兵庫県立こども病院専攻医主体の勉強会である。現在は尼崎総合医療センターも加わり、3病院で実施している。
兵庫県立こども病院小児救命救急センター長&感染対策部長
監修 笠井 正志
<編集のことば>
現場力で書き換えるアレルギー診療の現在形
初版が世に出てから、あっという間に4年が経った。あの頃はCOVID-19が猛威をふるい、マスクと消毒液とZoomに振り回される毎日だったはずなのに、今やそんな出来事すら忘れかけている。人間の忘却力と順応力はすごいものである。
その間、アレルギー診療の世界も大きく動いた。アトピー性皮膚炎の新薬ラッシュ、喘息の生物学的製剤も少しずつ普及し、確かに医学は前に進んでいる。だが、相変わらずスギ花粉が飛べば目をこすり、鼻水を垂らす子どもはいるし、喘息で入院する子もいる。食物アレルギーの対応に右往左往する現場も健在である。つまり、進化した情報と、変わらぬ日常のギャップをどう橋渡しするかが、今も昔も変わらぬ課題である。
初版には「読みやすくてすぐ使える」「当直のとき本当に助かる」といった声をたくさんいただいた。もちろん、「○○のところ、ちょっと薄いね」といったツッコミもあった。そういうところも含めて、“トリセツらしさ”として受け止めて、改訂に活かした。
今回の改訂でも意識したのは、著者の田中裕也先生のあの躍動感をそのまま活かすこと。勢いがありつつも親切で、脱線しそうでちゃんと戻ってくる、あのタッチである。勤務医から開業医へとステージを移した田中先生は、さらに実地感を増し、その中で新しいものをどのように日常診療に落とし込んでいくか? を語れるようになっていた。今回の改訂では、その「現場感」をギュッと詰め込んでくれたと思う。いつも暖かく見守って下さっている笠井正志先生にも感謝である。
というわけで、『小児アレルギーのトリセツ』プロジェクトは今も絶賛爆進中である。引き続き、愛のあるフィードバックをお待ちしている。
神戸市立医療センター中央市民病院小児科 医長
編集 岡藤 郁夫
偉大な教師は心に火をつける
アレルギー治療において、患者教育は薬物療法と同じくらい重要です。日々のケアを患者さんご自身が理解し、実践できるようなわかりやすい情報提供は欠かせません。そのためには、私たち医療者自身が正確な知識を身につけ、常に学び続けることが不可欠です。
「アレルギーは誰でもできる。それをより質高く実践すること」。この命題を多くの医療者に伝えるため、著者である田中裕也先生は常に情熱的に教育活動に取り組んでいます。
一番印象に残っているのは、KOBEセミナー*でのスキンケア指導ワークショップです。スキンケアの要点はp.82の図5にも記載されています。「石けんの泡で洗う」というシンプルな言葉だけでは、経験の少ない専攻医が具体的なイメージをもって患者指導を行うのは難しいものです。田中先生は、実際にバケツを使って「泡立てる」ことを楽しく実演してくださいました。その生き生きとした指導に、専攻医たちも夢中になっていました。まさに、偉大な教師の姿がそこにはありました。
教育の本質は、教える側の「どうしても伝えたい」という情熱が、学ぶ側の心に火をつけることにあると私は考えます。本書もまた、単なる情報の羅列ではありません。読者が自ら学び、成長しようとする力を育む、実践的な指南書となることを目指したものです。ぜひ、本書を通してアレルギー診療の新たな扉を開いてください。
*KOBEセミナーとは約10年前から続いている神戸中央市民病院小児科と兵庫県立こども病院専攻医主体の勉強会である。現在は尼崎総合医療センターも加わり、3病院で実施している。
兵庫県立こども病院小児救命救急センター長&感染対策部長
監修 笠井 正志
<編集のことば>
現場力で書き換えるアレルギー診療の現在形
初版が世に出てから、あっという間に4年が経った。あの頃はCOVID-19が猛威をふるい、マスクと消毒液とZoomに振り回される毎日だったはずなのに、今やそんな出来事すら忘れかけている。人間の忘却力と順応力はすごいものである。
その間、アレルギー診療の世界も大きく動いた。アトピー性皮膚炎の新薬ラッシュ、喘息の生物学的製剤も少しずつ普及し、確かに医学は前に進んでいる。だが、相変わらずスギ花粉が飛べば目をこすり、鼻水を垂らす子どもはいるし、喘息で入院する子もいる。食物アレルギーの対応に右往左往する現場も健在である。つまり、進化した情報と、変わらぬ日常のギャップをどう橋渡しするかが、今も昔も変わらぬ課題である。
初版には「読みやすくてすぐ使える」「当直のとき本当に助かる」といった声をたくさんいただいた。もちろん、「○○のところ、ちょっと薄いね」といったツッコミもあった。そういうところも含めて、“トリセツらしさ”として受け止めて、改訂に活かした。
今回の改訂でも意識したのは、著者の田中裕也先生のあの躍動感をそのまま活かすこと。勢いがありつつも親切で、脱線しそうでちゃんと戻ってくる、あのタッチである。勤務医から開業医へとステージを移した田中先生は、さらに実地感を増し、その中で新しいものをどのように日常診療に落とし込んでいくか? を語れるようになっていた。今回の改訂では、その「現場感」をギュッと詰め込んでくれたと思う。いつも暖かく見守って下さっている笠井正志先生にも感謝である。
というわけで、『小児アレルギーのトリセツ』プロジェクトは今も絶賛爆進中である。引き続き、愛のあるフィードバックをお待ちしている。
神戸市立医療センター中央市民病院小児科 医長
編集 岡藤 郁夫