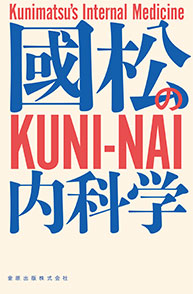Copyright© KANEHARA & Co., LTD. All Rights Reserved.
國松の内科学
全文が臨床の知。本物の総合内科医の脳内がすべて、ここに。

國松淳和は内科医である。臨床の傍らで数々の医学書を執筆し、その独創的な切り口は多くの人を惹きつけてきた。はたして、彼の頭のなかには広大な内科学の世界がどのように収まり、出力し続けているのだろうか。
本書はたったひとりの総合内科医の脳内を、たったひとつの本に著したものである。國松淳和、医書書き10年間の集大成。全編1700ページ超。200以上の内科疾患を網羅。一切の駄文なし。新しい内科学テキストの地平がいま開く。
本書はたったひとりの総合内科医の脳内を、たったひとつの本に著したものである。國松淳和、医書書き10年間の集大成。全編1700ページ超。200以上の内科疾患を網羅。一切の駄文なし。新しい内科学テキストの地平がいま開く。
序の章
1 國松の内科学
2 病歴聴取
3 身体診察
4 血液検査
5 画像検査
6 臨床推論
7 治療総論
8 外来診療
9 救急対応
10 入院診療
11 コミュニケーションスキル
12 タイムマネジメント
13 勉強法
14 カルテの書き方
実の章
1.呼吸器
1 慢性閉塞性肺疾患
2 間質性肺炎
3 過敏性肺炎
4 好酸球性肺炎
5 気管支拡張症
6 肺癌
7 縦隔腫瘍
8 気胸
9 閉塞性睡眠時無呼吸症候群
10 咳過敏症症候群
2.消化器
1 大腸憩室出血
2 虚血性大腸炎
3 下部消化管出血
4 上部消化管出血
5 胃・十二指腸潰瘍
6 胃食道逆流症
7 機能性消化管障害・上部
8 機能性消化管障害・下部
9 食道アカラシア
10 上腸間膜動脈症候群
11 急性虫垂炎
12 大腸憩室炎
13 急性腸管虚血
14 小腸閉塞
15 大腸閉塞
16 炎症性腸疾患
17 好酸球性消化管疾患
18 食道癌
19 胃癌
20 大腸癌
21 蛋白漏出性胃腸症
22 胃アニサキス症
3.肝・胆・膵
1 急性胆嚢炎/胆石症
2 急性胆管炎
3 肝膿瘍
4 非アルコール性脂肪性肝疾患・非アルコール性脂肪性肝炎
5 慢性B型肝炎
6 慢性C型肝炎
7 自己免疫性肝炎
8 原発性胆汁性胆管炎・原発性硬化性胆管炎
9 肝硬変症
10 肝細胞癌
11 胆道癌
12 急性膵炎
13 慢性膵炎
14 膵癌
4.循環器
1 高血圧症
2 急性心不全
3 急性冠症候群
4 大動脈解離
5 大動脈弁狭窄症
6 僧帽弁閉鎖不全症
7 大動脈弁閉鎖不全症
8 頻脈性不整脈
9 心房細動
10 徐脈性不整脈
11 肺血栓塞栓症
12 肺高血圧症
13 収縮性心膜炎
14 急性心膜炎
15 心筋炎
16 たこつぼ型心筋症
17 末梢動脈疾患
18 遺伝性大動脈疾患
5.神経・精神
1 くも膜下出血
2 脳出血―くも膜下出血以外
3 慢性硬膜下血腫
4 脳梗塞
5 脳腫瘍
6 特発性正常圧水頭症
7 てんかん
8 自己免疫性脳炎
9 多発性硬化症
10 脊髄梗塞
11 重症筋無力症
12 アルツハイマー病
13 筋萎縮性側索硬化症
14 脊髄小脳変性症
15 パーキンソン病
16 うつ病
17 ギラン・バレー症候群
18 フィッシャー症候群
19 ベル麻痺
20 ニューロパチー
21 良性発作性頭位めまい症
22 片頭痛
23 本態性振戦
24 レストレスレッグス症候群
25 アルコール離脱症候群
26 セロトニン症候群
6.腎・泌尿器・電解質
1 急性電解質異常
2 慢性電解質異常
3 慢性腎臓病
4 急性腎障害
5 急速進行性糸球体腎炎
6 尿細管間質性腎炎
7 ネフローゼ症候群
8 IgA腎症
9 腎梗塞
10 コレステロール塞栓症
11 尿路結石
12 精巣捻転
13 精巣上体炎
14 前立腺肥大症
7.代謝・内分泌
1 バセドウ病
2 無痛性甲状腺炎
3 亜急性甲状腺炎
4 甲状腺機能低下症
5 甲状腺腫瘍
6 副甲状腺機能亢進症
7 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群
8 中枢性尿崩症
9 下垂体腫瘍
10 ACTH単独欠損症
11 副腎不全
12 クッシング症候群
13 原発性アルドステロン症
14 褐色細胞腫・パラガングリオーマ
15 1型糖尿病
16 2型糖尿病
17 高血糖緊急症
18 脂質異常症
19 骨粗鬆症
8.血液
1 急性骨髄性白血病
2 骨髄異形成腫瘍
3 骨髄増殖性腫瘍
4 慢性骨髄性白血病
5 鉄欠乏性貧血
6 巨赤芽球性貧血
7 自己免疫性溶血性貧血
8 血栓性血小板減少性紫斑病
9 特発性血小板減少性紫斑病
10 悪性リンパ腫・総論
11 悪性リンパ腫・オムニバス
12 多発性骨髄腫
13 POEMS症候群
14 アミロイドーシス
15 キャッスルマン病
16 TAFRO症候群
17 後天性血友病A
18 好酸球増多症候群
9.アレルギー
1 気管支喘息
2 アナフィラキシー
3 食物依存性運動誘発アナフィラキシー
4 口腔アレルギー症候群
5 薬疹―典型・一般的なもの
6 薬疹―特殊・重症なもの
7 アレルギー性鼻炎
10.自己免疫・炎症性疾患
1 関節リウマチ
2 リウマチ性多発筋痛症
3 高齢発症関節炎
4 巨細胞性動脈炎
5 高安動脈炎
6 IgA血管炎
7 結節性動脈炎
8 顕微鏡的多発血管炎
9 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
10 多発血管炎性肉芽腫症
11 IgG4関連疾患
12 サルコイドーシス
13 結節性紅斑
14 菊池病
15 全身性エリテマトーデス
16 抗リン脂質抗体症候群
17 シェーグレン症候群
18 筋炎
19 全身性強皮症
20 脊椎関節炎
21 ベーチェット病
22 家族性地中海熱
23 結晶性関節炎
24 成人スティル病
25 混合性結合組織病
11.感染症
1 急性腸炎―キャンピロバクターを除く
2 キャンピロバクター腸炎
3 かぜ
4 市中肺炎
5 院内肺炎
6 誤嚥性肺炎
7 急性膿胸
8 敗血症性肺塞栓
9 結核症
10 非結核性抗酸菌症
11 結核性リンパ節炎
12 伝染性単核球症
13 サイトメガロウイルス感染症
14 ヒトパルボウイルスB19感染症
15 急性HIV感染症
16 麻疹・風疹
17 水痘・帯状疱疹
18 敗血症
19 トキシックショック症候群
20 壊死性筋膜炎
21 蜂窩織炎
22 感染性心内膜炎
23 髄膜炎・脳炎
24 化膿性関節炎
25 クロストリディオイデス・ディフィシル感染症
26 急性膀胱炎
27 腎盂腎炎
28 性感染症
12.女性疾患
1 骨盤内炎症性疾患
2 異所性妊娠
3 卵巣腫瘍茎捻転
4 子宮内膜症
5 月経困難症
6 月経前症候群
7 更年期障害
8 乳癌
13.救急・マイナー疾患
1 急性閉塞隅角緑内障
2 突発性難聴
3 転移性骨腫瘍
4 頸椎症
5 熱中症
1 國松の内科学
2 病歴聴取
3 身体診察
4 血液検査
5 画像検査
6 臨床推論
7 治療総論
8 外来診療
9 救急対応
10 入院診療
11 コミュニケーションスキル
12 タイムマネジメント
13 勉強法
14 カルテの書き方
実の章
1.呼吸器
1 慢性閉塞性肺疾患
2 間質性肺炎
3 過敏性肺炎
4 好酸球性肺炎
5 気管支拡張症
6 肺癌
7 縦隔腫瘍
8 気胸
9 閉塞性睡眠時無呼吸症候群
10 咳過敏症症候群
2.消化器
1 大腸憩室出血
2 虚血性大腸炎
3 下部消化管出血
4 上部消化管出血
5 胃・十二指腸潰瘍
6 胃食道逆流症
7 機能性消化管障害・上部
8 機能性消化管障害・下部
9 食道アカラシア
10 上腸間膜動脈症候群
11 急性虫垂炎
12 大腸憩室炎
13 急性腸管虚血
14 小腸閉塞
15 大腸閉塞
16 炎症性腸疾患
17 好酸球性消化管疾患
18 食道癌
19 胃癌
20 大腸癌
21 蛋白漏出性胃腸症
22 胃アニサキス症
3.肝・胆・膵
1 急性胆嚢炎/胆石症
2 急性胆管炎
3 肝膿瘍
4 非アルコール性脂肪性肝疾患・非アルコール性脂肪性肝炎
5 慢性B型肝炎
6 慢性C型肝炎
7 自己免疫性肝炎
8 原発性胆汁性胆管炎・原発性硬化性胆管炎
9 肝硬変症
10 肝細胞癌
11 胆道癌
12 急性膵炎
13 慢性膵炎
14 膵癌
4.循環器
1 高血圧症
2 急性心不全
3 急性冠症候群
4 大動脈解離
5 大動脈弁狭窄症
6 僧帽弁閉鎖不全症
7 大動脈弁閉鎖不全症
8 頻脈性不整脈
9 心房細動
10 徐脈性不整脈
11 肺血栓塞栓症
12 肺高血圧症
13 収縮性心膜炎
14 急性心膜炎
15 心筋炎
16 たこつぼ型心筋症
17 末梢動脈疾患
18 遺伝性大動脈疾患
5.神経・精神
1 くも膜下出血
2 脳出血―くも膜下出血以外
3 慢性硬膜下血腫
4 脳梗塞
5 脳腫瘍
6 特発性正常圧水頭症
7 てんかん
8 自己免疫性脳炎
9 多発性硬化症
10 脊髄梗塞
11 重症筋無力症
12 アルツハイマー病
13 筋萎縮性側索硬化症
14 脊髄小脳変性症
15 パーキンソン病
16 うつ病
17 ギラン・バレー症候群
18 フィッシャー症候群
19 ベル麻痺
20 ニューロパチー
21 良性発作性頭位めまい症
22 片頭痛
23 本態性振戦
24 レストレスレッグス症候群
25 アルコール離脱症候群
26 セロトニン症候群
6.腎・泌尿器・電解質
1 急性電解質異常
2 慢性電解質異常
3 慢性腎臓病
4 急性腎障害
5 急速進行性糸球体腎炎
6 尿細管間質性腎炎
7 ネフローゼ症候群
8 IgA腎症
9 腎梗塞
10 コレステロール塞栓症
11 尿路結石
12 精巣捻転
13 精巣上体炎
14 前立腺肥大症
7.代謝・内分泌
1 バセドウ病
2 無痛性甲状腺炎
3 亜急性甲状腺炎
4 甲状腺機能低下症
5 甲状腺腫瘍
6 副甲状腺機能亢進症
7 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群
8 中枢性尿崩症
9 下垂体腫瘍
10 ACTH単独欠損症
11 副腎不全
12 クッシング症候群
13 原発性アルドステロン症
14 褐色細胞腫・パラガングリオーマ
15 1型糖尿病
16 2型糖尿病
17 高血糖緊急症
18 脂質異常症
19 骨粗鬆症
8.血液
1 急性骨髄性白血病
2 骨髄異形成腫瘍
3 骨髄増殖性腫瘍
4 慢性骨髄性白血病
5 鉄欠乏性貧血
6 巨赤芽球性貧血
7 自己免疫性溶血性貧血
8 血栓性血小板減少性紫斑病
9 特発性血小板減少性紫斑病
10 悪性リンパ腫・総論
11 悪性リンパ腫・オムニバス
12 多発性骨髄腫
13 POEMS症候群
14 アミロイドーシス
15 キャッスルマン病
16 TAFRO症候群
17 後天性血友病A
18 好酸球増多症候群
9.アレルギー
1 気管支喘息
2 アナフィラキシー
3 食物依存性運動誘発アナフィラキシー
4 口腔アレルギー症候群
5 薬疹―典型・一般的なもの
6 薬疹―特殊・重症なもの
7 アレルギー性鼻炎
10.自己免疫・炎症性疾患
1 関節リウマチ
2 リウマチ性多発筋痛症
3 高齢発症関節炎
4 巨細胞性動脈炎
5 高安動脈炎
6 IgA血管炎
7 結節性動脈炎
8 顕微鏡的多発血管炎
9 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
10 多発血管炎性肉芽腫症
11 IgG4関連疾患
12 サルコイドーシス
13 結節性紅斑
14 菊池病
15 全身性エリテマトーデス
16 抗リン脂質抗体症候群
17 シェーグレン症候群
18 筋炎
19 全身性強皮症
20 脊椎関節炎
21 ベーチェット病
22 家族性地中海熱
23 結晶性関節炎
24 成人スティル病
25 混合性結合組織病
11.感染症
1 急性腸炎―キャンピロバクターを除く
2 キャンピロバクター腸炎
3 かぜ
4 市中肺炎
5 院内肺炎
6 誤嚥性肺炎
7 急性膿胸
8 敗血症性肺塞栓
9 結核症
10 非結核性抗酸菌症
11 結核性リンパ節炎
12 伝染性単核球症
13 サイトメガロウイルス感染症
14 ヒトパルボウイルスB19感染症
15 急性HIV感染症
16 麻疹・風疹
17 水痘・帯状疱疹
18 敗血症
19 トキシックショック症候群
20 壊死性筋膜炎
21 蜂窩織炎
22 感染性心内膜炎
23 髄膜炎・脳炎
24 化膿性関節炎
25 クロストリディオイデス・ディフィシル感染症
26 急性膀胱炎
27 腎盂腎炎
28 性感染症
12.女性疾患
1 骨盤内炎症性疾患
2 異所性妊娠
3 卵巣腫瘍茎捻転
4 子宮内膜症
5 月経困難症
6 月経前症候群
7 更年期障害
8 乳癌
13.救急・マイナー疾患
1 急性閉塞隅角緑内障
2 突発性難聴
3 転移性骨腫瘍
4 頸椎症
5 熱中症
國松の内科学
この教科書がどんな本なのか、どう読めばいいのか。はじめにそれを説明したいとは思うのだが、なんだかしっくり来ない。この本は『國松の内科学』である。とにかく読めばよい。読めばわかる。読めば内容も読み方もわかる。よって、以下に記すことは大いなる蛇足である。
<本書が内科学について語り得るもの>
単著で内科学全体の教科書を書くことの良さは、執筆を始めてから、そして書き終わってから気づいた。この本は、企画や執筆開始の段階で、完成したときの青写真などはなく「とにかく内科学の本を書こう」から始まった。緻密な計画書はなかった。
この本は疾患について説明しているのが基本的な内容だが、一般に各疾患にはその概要や診断、治療といったポイントや要素が当然含まれる。共著の場合は、ある程度そのような項目見出しを揃え、可能な限りテンプレート化しそれに基づいて各項目のフォームを埋めるような感じで執筆されるだろう。
この本を作り始めてから分かったのは、疾患によって重要点とその分量が異なるということだった。診断が重要なもの、治療が重要なもの、診断は診断でも症状からいかに気づくかが重要なもの、検査が重要なもの、はじめの概要や病態生理のようなことがとにかく重要であるものなど、各項目や重要点が同じ比率で考えていい疾患はひとつとしてなかった。
よって本書では、各疾患のはじめの書き出しは「理解の架け橋」というタイトルで統一した。このことの本質は、あえて曖昧にしてあるということである。つまり、概要や概念、総論、疫学、病態生理、疾患の分類、重要な初期症候など、書きたいことは各疾患で異なり、記述を統一できないことから、疾患ごとに書かれた内容の種類やその比重は異なっている。単著で書く場合、当然原稿の内容は“original”であるから、その疾患について(私が)思いを馳せ説明したい順かつ重要な順に書く。こうであるから、疾患ごとにその内訳が異なってくるというわけである。これを独りよがりと言うなら言うがいい。
また記述するうえで重視したのは、各疾患の疑いかたや診断までの現実的な話、その疾患の自然経過、そして治療である。特に治療は、その疾患を専門的に扱わない医師が対症療法を行うことがあるような場合には、それについて具体的に記述するように努めた。
「理解の架け橋」以外の項目でも、ある疾患では「疑いかた」が長かったり、ある疾患では「治療」の記述が短かったりしている。この理由は、繰り返すようであるが疾患ごとに重要点とその比率が異なるためである。
<本書の読みかたと用いかた>
読みかたなど、私が書かずとも自由に読んでくれたらいいが、イメージした具体的な場面についてふたつ示す。
ひとつは、読者らが勤務する医療現場での実際の臨床の傍らで、ある疾患の何かについて議論が起こったときである。「じゃあクニナイ(※『國松の内科学』つまり本書のこと)ではどう書かれていただろうか」と思って本書を開いてみてほしい。議論が起こったということは、答えがないということであって、そういうときに求められるのは個人の意見だと思う。本書は『國松の内科学』であるから、パーソナルな視座での記述がふんだんにされてある。
もうひとつは、いわゆる初学者による内科学の座学である。あえて具体的にいえば、学生(医学でも薬学でも看護学でも何でもいい)や初期研修医、あるいは医師以外の医療者であるが、彼ら・彼女らがある疾患の臨床の側面について学ぼうとするときに、本書の内容を通読してみてほしいと思っている。当たり前だが重要なことを記述してあるので、勉強する際に重要点の勾配が掴みやすくなると信じている。
そう。もうこれは、信じるしかないのである。一人で書き切ることで、間違いなく保証できるのは記述の一貫性である。これだけは大丈夫である。ただ、医学の進歩は著しく、また私の臨床経験の乏しさや理解の及ばなさから、未熟あるいは不足の部分も多くあると思う。これに対しては謙虚に対応していこうと思っている。できれば私より年下の医療者や学生からの意見や訂正がほしい。若者との議論が一番勉強になるからだ。同輩からの励ましもうれしい。
<『國松の内科学』が目指すもの>
話を少し戻す。単著で書いたことで、失ったこと、あるいは記述が及ばないことはたくさんあるだろうと思う。私はさすがにそれをどうでもいいとは思っていない。私を上回る医師はたくさんいるし、複数で執筆すればこういうことが書けたなあとか内容の精度を上げられたなあというのは山ほどある。
目指したのは、完璧すぎないのに理解しやすい記述である。書き尽くして全部のことを盛り込むのは、きっとそれはあまり頭を使っていない。が、書いたほうがいいのにカットする営為は、臨床医かつ医書書きを生業とする私の技芸だと思っている。この本を世に出すことは、多くの重要と思われる事柄を捨てる(=記述しない)ことでかえって理解が深まるのではないか、という私の医書書きとしての挑戦でもある。
私や担当した編集者にしかわからない解像度で、そうした仕掛けを存分に盛り込んだ。大事なことは細部に宿らせている。再び言うが、これは信じてもらうしかない。
蛇足が随分長かった。この本ができるだけ多くの人の目に留まり、そしてできるだけ多くの人がこの本を読み通し、膝を打ってくれることを願っている。
この教科書がどんな本なのか、どう読めばいいのか。はじめにそれを説明したいとは思うのだが、なんだかしっくり来ない。この本は『國松の内科学』である。とにかく読めばよい。読めばわかる。読めば内容も読み方もわかる。よって、以下に記すことは大いなる蛇足である。
<本書が内科学について語り得るもの>
単著で内科学全体の教科書を書くことの良さは、執筆を始めてから、そして書き終わってから気づいた。この本は、企画や執筆開始の段階で、完成したときの青写真などはなく「とにかく内科学の本を書こう」から始まった。緻密な計画書はなかった。
この本は疾患について説明しているのが基本的な内容だが、一般に各疾患にはその概要や診断、治療といったポイントや要素が当然含まれる。共著の場合は、ある程度そのような項目見出しを揃え、可能な限りテンプレート化しそれに基づいて各項目のフォームを埋めるような感じで執筆されるだろう。
この本を作り始めてから分かったのは、疾患によって重要点とその分量が異なるということだった。診断が重要なもの、治療が重要なもの、診断は診断でも症状からいかに気づくかが重要なもの、検査が重要なもの、はじめの概要や病態生理のようなことがとにかく重要であるものなど、各項目や重要点が同じ比率で考えていい疾患はひとつとしてなかった。
よって本書では、各疾患のはじめの書き出しは「理解の架け橋」というタイトルで統一した。このことの本質は、あえて曖昧にしてあるということである。つまり、概要や概念、総論、疫学、病態生理、疾患の分類、重要な初期症候など、書きたいことは各疾患で異なり、記述を統一できないことから、疾患ごとに書かれた内容の種類やその比重は異なっている。単著で書く場合、当然原稿の内容は“original”であるから、その疾患について(私が)思いを馳せ説明したい順かつ重要な順に書く。こうであるから、疾患ごとにその内訳が異なってくるというわけである。これを独りよがりと言うなら言うがいい。
また記述するうえで重視したのは、各疾患の疑いかたや診断までの現実的な話、その疾患の自然経過、そして治療である。特に治療は、その疾患を専門的に扱わない医師が対症療法を行うことがあるような場合には、それについて具体的に記述するように努めた。
「理解の架け橋」以外の項目でも、ある疾患では「疑いかた」が長かったり、ある疾患では「治療」の記述が短かったりしている。この理由は、繰り返すようであるが疾患ごとに重要点とその比率が異なるためである。
<本書の読みかたと用いかた>
読みかたなど、私が書かずとも自由に読んでくれたらいいが、イメージした具体的な場面についてふたつ示す。
ひとつは、読者らが勤務する医療現場での実際の臨床の傍らで、ある疾患の何かについて議論が起こったときである。「じゃあクニナイ(※『國松の内科学』つまり本書のこと)ではどう書かれていただろうか」と思って本書を開いてみてほしい。議論が起こったということは、答えがないということであって、そういうときに求められるのは個人の意見だと思う。本書は『國松の内科学』であるから、パーソナルな視座での記述がふんだんにされてある。
もうひとつは、いわゆる初学者による内科学の座学である。あえて具体的にいえば、学生(医学でも薬学でも看護学でも何でもいい)や初期研修医、あるいは医師以外の医療者であるが、彼ら・彼女らがある疾患の臨床の側面について学ぼうとするときに、本書の内容を通読してみてほしいと思っている。当たり前だが重要なことを記述してあるので、勉強する際に重要点の勾配が掴みやすくなると信じている。
そう。もうこれは、信じるしかないのである。一人で書き切ることで、間違いなく保証できるのは記述の一貫性である。これだけは大丈夫である。ただ、医学の進歩は著しく、また私の臨床経験の乏しさや理解の及ばなさから、未熟あるいは不足の部分も多くあると思う。これに対しては謙虚に対応していこうと思っている。できれば私より年下の医療者や学生からの意見や訂正がほしい。若者との議論が一番勉強になるからだ。同輩からの励ましもうれしい。
<『國松の内科学』が目指すもの>
話を少し戻す。単著で書いたことで、失ったこと、あるいは記述が及ばないことはたくさんあるだろうと思う。私はさすがにそれをどうでもいいとは思っていない。私を上回る医師はたくさんいるし、複数で執筆すればこういうことが書けたなあとか内容の精度を上げられたなあというのは山ほどある。
目指したのは、完璧すぎないのに理解しやすい記述である。書き尽くして全部のことを盛り込むのは、きっとそれはあまり頭を使っていない。が、書いたほうがいいのにカットする営為は、臨床医かつ医書書きを生業とする私の技芸だと思っている。この本を世に出すことは、多くの重要と思われる事柄を捨てる(=記述しない)ことでかえって理解が深まるのではないか、という私の医書書きとしての挑戦でもある。
私や担当した編集者にしかわからない解像度で、そうした仕掛けを存分に盛り込んだ。大事なことは細部に宿らせている。再び言うが、これは信じてもらうしかない。
蛇足が随分長かった。この本ができるだけ多くの人の目に留まり、そしてできるだけ多くの人がこの本を読み通し、膝を打ってくれることを願っている。
- 医書.jpで購入される方は
こちらから (外部サイトに移動します) - m3.comで購入される方は
こちらから (外部サイトに移動します)