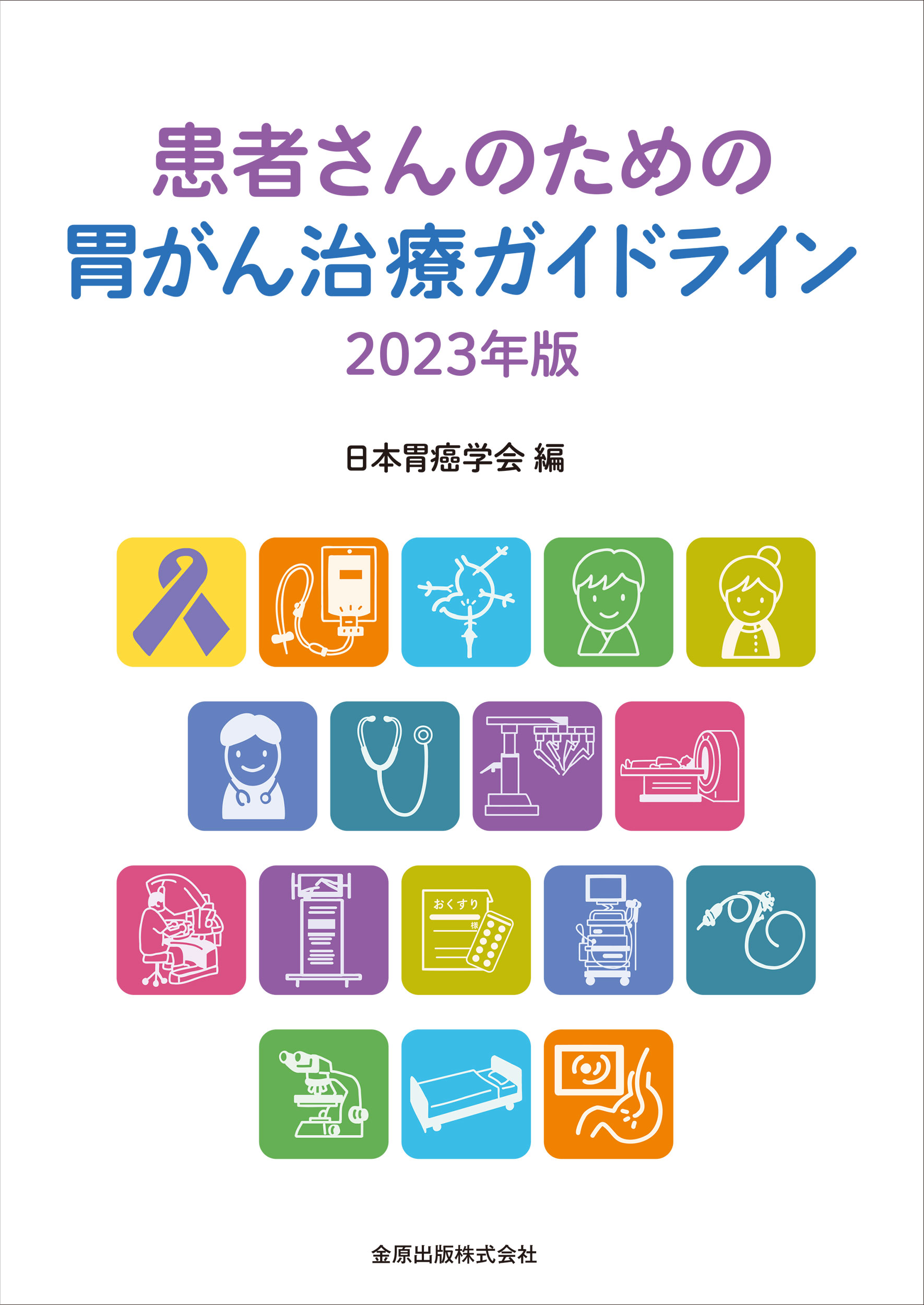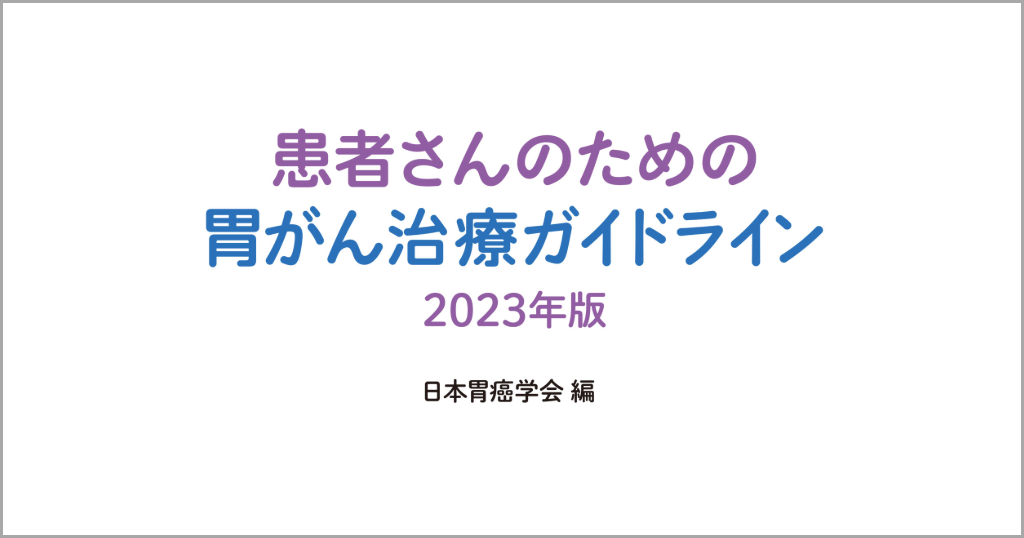日本胃癌学会は日本における胃がんの研究・診療の中心となって活動している学術団体です。その日本胃癌学会が編集した患者さん向けの書籍「患者さんのための胃がん治療ガイドライン 2023年版」から,内容の一部をご紹介します。
なぜ胃がんになるのですか?
胃がんの原因としては遺伝的因子(いでんてきいんし,遺伝による原因)と環境的因子(かんきょうてきいんし,環境による原因)があります。遺伝的因子として,極めて稀ですが,家族性(かぞくせい)胃がんが知られています。細胞と細胞の接着に関わるタンパク質の遺伝子であるCDH1 やαカテニンに変異があると,びまん浸潤型の胃がんを高い確率で発症します。他にも,BRCA1 遺伝子の異常により発症する遺伝性乳がん卵巣がん症候群〔いでんせいにゅうがんらんそうがんしょうこうぐん,HBOC(エイチボック),高い確率で乳がんや卵巣がんを発症します〕や,APC という遺伝子異常により発症する家族性大腸腺腫症(かぞくせいだいちょうせんしゅしょう),ミスマッチ修復酵素の遺伝子異常が原因となるリンチ症候群(リンチしょうこうぐん)などで,胃がんのリスクが増加することが知られていますが,胃がんの発生との間に明確な関連は未だ解明されていません。
日本における胃がんの発生には遺伝的因子よりも環境的因子がより重要と考えられています。家族内で高頻度に胃がんが発症することがありますが,幼少期から同じ環境で生活し,食品の嗜好が似通ってしまうことが原因となるものと思われます。
環境による因子としてはピロリ菌(ピロリきん)の感染が最もよく知られています。幼少期のピロリ菌感染によってゆっくりと胃粘膜に炎症が引き起こされ〔慢性萎縮性胃炎(まんせいいしゅくせいいえん)〕,そこに塩分を過量に摂取すると胃がんが発生しやすくなります(Q & A 総論4:44 ページ参照)。一方で,野菜や果物はほぼ確実に胃がんのリスクを軽減するとされています。緑茶の摂取も胃がんの発生を抑制させる可能性があることが報告されています。喫煙(きつえん)は胃がんを含めて10 種類のがんとの因果関係が証明されています。飲酒(いんしゅ)によって噴門部(ふんもんぶ)がんが増えることも指摘されています。ピロリ菌以外の微生物としては,日本では成人の約90%が感染しているエプスタイン・バー(EB)ウイルスによっても胃がんが発生することが知られていますが,発がんのメカニズムは不明です。
胃がんを予防するには,ピロリ菌の感染を予防し(感染した場合は除菌し),塩分の濃い食事を控え,野菜や果物を充分に摂取しましょう。さらに,喫煙や過度の飲酒は控えることも大切です。
検診は毎年受けたほうがよいですか?
対策型検診(たいさくがたけんしん)とは,がんの早期発見・早期治療により対象集団全体のがん死亡率を減少させることを目的に,公的資金を用いて行われる検診です。現在,日本の対策型胃がん検診(住じゅう民みん検けん診しん)では,胃部X線検査(いぶエックスせんけんさ)さ または胃内視鏡検査(いないしきょうけんさ)が行われています。「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(厚生労働省)によると,胃がん検診が推奨される年齢は50 歳以上の健常者で,原則として2 年に1 回行うこととなっています。ただし,胃部X 線検査に関しては今までどおり,年に1 回の実施も可能となっています。
胃部X 線検査
発泡剤(胃をふくらませる薬)とバリウム(造影剤)を飲み,胃の中の粘膜を観察する検査です。本検査で胃粘膜に異常を認めた場合には精査目的に,胃内視鏡検査を受けます。1~2 年に1 回の検診受診となっています。
胃内視鏡検査
口または鼻から胃の中に内視鏡を挿入し,胃の内部を観察する検査です。検査時に疑わしい部位が見つかれば,そのまま生検(組織を採取する)を行う場合もあります。2 年に1 回の検診受診となっています。
胃がんリスク層別化検診
萎縮性胃炎のマーカーである血清ペプシノゲン検査(けっせいペプシノゲンけんさ)とヘリコバクターピロリ抗体検査(ヘリコバクターピロリこうたいけんさ)の結果を用いて胃がんのリスク評価を行い,リスクに応じて1~5 年に1回の胃内視鏡検査を行う方法です。現時点では,死亡率減少効果を判断する証拠が不十分であるため,対策型胃がん検診として実施することは勧められていません。
日本での胃がんの95%以上がヘリコバクターピロリ(ピロリ菌)感染に伴うものであることを考えると胃がんリスク層別化検診が最も効率的でありますが,血液検査のみでの感染検査では精度が下がることなどの問題点が残っており,いまだ検討が必要な段階となっています。
以上より,対策型検診においては,胃部X 線検査または胃内視鏡検査が推奨されており,原則は2 年に1 回の検診を受けることが勧められています。胃部X 線検査にて異常が指摘された場合には,精査目的の胃内視鏡検査を必ず受けることも大切です。
胃がんはどこに転移しますか?
胃がんの転移形式は大きく分けて3 つあります。リンパ行性転移,血行性転移,腹膜播種性転移です〈3)転移:11 ページ参照〉。
リンパ行性転移(リンパこうせいてんい)とは,粘膜下層まで浸潤した胃がんが胃壁内のリンパ管に浸潤し,リンパの流れに乗ってリンパ節に運ばれ,そこで転移を形成したものです。リンパの流れは胃の周囲から動脈に沿って大動脈へと向かいます。さらにそこから胸管という太いリンパ管に合流し,左の鎖骨の裏側にある太い静脈に注ぎます。がんの進行に伴い,リンパ節転移もその流れに沿った部位に形成されます。胃の周囲から大動脈の手前までの腹部のリンパ節は領域リンパ節(りょういきリンパせつ)と定義されていて,手術で取り除くことが可能です。それより遠くのリンパ節は遠隔リンパ節(えんかくリンパせつ)とされ,遠隔転移(えんかくてんい)の一つとして扱われます。
血行性転移(けっこうせいてんい)とは,粘膜下層まで浸潤した胃がんが胃壁内の静脈に浸潤し,血液の流れによって全身に広がり,遠い臓器に転移を形成したものです。胃の静脈はほとんど門脈という太い血管に流入し,肝臓に注がれます。肝臓を通り抜けた血液は全身の循環に回ります。したがって胃がんの血行性転移は肝臓に起こることが最も多く,次いで,肺,骨〔骨髄(こつずい)〕,脳,副腎(ふくじん)などです。少数の肝臓への転移を除いて手術で転移巣を取り除くことはできません。
腹膜播種性転移(ふくまくましゅせいてんい)とは,胃壁の外まで浸潤した胃がんが胃壁から遊離して腹腔内に散らばり,お腹の内側を覆っている腹膜という所にくっついて転移を形成したものです。胃の近くにある一部の少数の転移を除いて腹膜播種性転移は手術で取り除くことはできません。全身薬物療法の適応(対象)となります。腹膜播種性転移はCT 検査やMRI 検査,PET 検査で診断することが困難なため,疑わしい場合は全身麻酔をかけて腹腔鏡を使用して観察し,生検により確定診断を得ます〔審査腹腔鏡(しんさふくくうきょう)〕。お腹の中にがん細胞が遊離した(散らばった)状態を細胞診で診断した場合も遠隔転移と見なされ,ステージⅣと診断されます。腹膜播種性転移は,胃の周囲の大たい網もうという脂肪の膜,小腸や大腸の壁やその膜,尿管(にょうかん),総胆管(そうたんかん),臍(へそ),骨盤の一番深いところ〔ダグラス窩(ダグラスか)といいます〕など,腹腔内のどこにでも形成されます。卵巣にも転移を形成する場合があり,これも腹膜播種性転移の一つの型と考えられています。腹膜播種性転移が高度になると腹膜に炎症を生じ腹水が貯留(お腹の中に水が貯まる)してきます。この状態をがん性腹膜炎(がんせいふくまくえん)といいます。
患者さんのための胃がん治療ガイドライン 2023年版
胃がんの専門家である日本胃癌学会の先生たちが,患者さんやご家族のために胃がんの検査から手術,内視鏡治療,薬物療法など治療まで,科学的な根拠をもとに丁寧に解説した,安心できる1冊。19年ぶりの改訂で,Q&Aが大幅に増え,手術後の生活や薬物療法で使う薬の種類など,患者さんの疑問により多くお応えできるようになりました。医療者の方にも患者さんとのコミュニケーションツールとして,おすすめです。